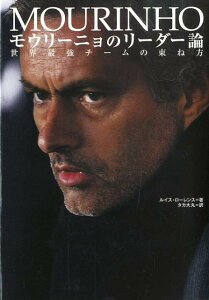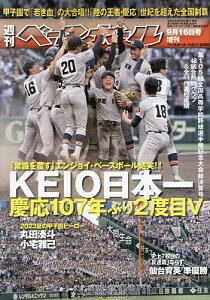「天才」と呼ばれる少年だった。
柿谷曜一朗(かきたに・よういちろう)
3歳でサッカー・ボールを蹴りはじめ、4歳でセレッソ大阪の下部組織に入団。才能の突出は誰の目にも明らかだった。
12歳頃からは、もはや途轍もなかった。
16歳(高校1年生)にして早、セレッソ大阪に入団。クラブ史上最年少でプロ契約(2006)。
本人いわく「わけわからん髪型」をした柿谷は、その入団会見でふてぶてしくもこう言い放った。
「僕がボール持ったときは、ぜひ期待しといて下さい」
2007年、17歳以下のW杯(U-17)で柿谷は驚異的なロングシュートを決める。なんとハーフウェイ・ライン付近から強豪フランスのゴールを破った。まるでベッカム(イングランド)を思わせるスーパーゴール。
この大会、日本は12年ぶりに優勝。
そのMVP(最優秀選手賞)を授かったのは、他ならぬ「天才」柿谷曜一朗であった。
■8番
入団したセレッソ大阪には、柿谷にとってのヒーローがいた。
「ミスター・セレッソ」、元日本代表の森島寛晃(もりしま・ひろあき)。
彼のつけていたセレッソのエースナンバー「8番」がたまらなくカッコよかった。
「森島さんのために『8番の似合う男』になります」
これは森島に送ったスパイクに柿谷が書いたメッセージである。柿谷はいつか「憧れの8番」を必ず受け継ぐと森島に誓っていたのであった。
ところが、その願いはそう簡単には叶わなかった。2008年に引退した森島から「8番」を受け取ったのは香川真司(かがわ・しんじ)。
香川は柿谷の一つ年上で、セレッソには同期入団であった。
柿谷「学校いくときは一緒に行ってました。ほんまアホなんすよ、二人して。アホって言ったらシンジくん(香川)に悪いけど」
柿谷は大阪生まれの大阪育ち。自称「大阪のクソガキ」。香川は神戸生まれ。
当初、世間の評価は圧倒的に柿谷が優っていた。セレッソ大阪のクルピ監督もそう見ていた。
クルピ監督「香川のほうがゴールに向かう意識は高いが、柿谷は技術的にもっと洗練されていた」
それでも、プロとして先に花開いたのは香川真司。プロ入り2年間で21得点を叩き上げた。一方の天才・柿谷は同じ2年間でわずか2得点…。
ベンチすら遠ざかってしまった柿谷。
少年時代からの憧れだった森島選手の引退セレモニー(2008)。その時に行われた試合のベンチにも柿谷は入れてもらえなかった。
エースナンバー「8番」が香川の手にわたるのは必然だった。
「天才」は、まずここでつまづいた。
■遅刻
「17〜19歳ぐらいのセレッソにいた時代っていうのは、プロサッカー選手ではなかったかな」
柿谷曜一郎は当時をそう振り返る。
反抗心と捨て鉢な気持ちとが相まって、柿谷は練習への「遅刻」を繰り返すようになる。
柿谷「試合に出れてないから遅刻したんじゃなくて、遅刻してもせんでも試合には出られへんやん、って。『別に、だから何』っていう態度をとってたしね」
大阪のクソガキは「問題児」の烙印を押された。
柿谷「まぁ、調子に乗ってたんでしょうね。ずっとセレッソでやってて、セレッソでプロんなって。そりゃ皆んなオレに注目するやろって、ちょっと舐めてたとこもあったし」
そして遂に、クルピ監督の逆鱗に触れる。
柿谷、6度目の遅刻にクルピ監督は「すべてのサポーターやクラブに対しての裏切りだ。相当高額な罰金を科した」と怒りを爆発させた。
2009年6月、柿谷曜一朗は懲罰的な措置により「J2徳島ヴォルディス」に放出される(期限付きレンタル移籍)。
当時を柿谷はこう振り返る。
「どう考えてもセレッソの一員じゃなかったしね。まぁ、逃げるっていう言葉がもしかしたら正解かもしんないすけど。でも、『オレはこのチームにおったらあかん』と思ったのも事実やし」
天才の舵は、すっかり狂ってしまっていた。
■徳島
柿谷曜一朗、21歳。
生まれ親しんだ大阪を離れ、独り四国・徳島へ。
新たなチームメイトとなった7歳年上の濱田武は言う。
「寂しがり屋じゃないですか。たぶん誰かおって欲しいんじゃないですか」
兄貴分となった濱田は、朝になると「曜一郎、行くで」と起こしてやる。
濱田「外で待ってる時もあるんすけど、ぜんぜん来ぉへんなぁと思ったら、また寝てたりとか(笑)」
鳴かず飛ばずだった天才・柿谷は、この徳島でついに才能を解き放つ。
固定されたレギュラーのなかった徳島ヴォルティスでは、日々の競争がより激しく、それが柿谷の性には合っていた。
柿谷は「Jリーグ屈指」といわれるテクニックでレギュラーに定着。抜きん出たシュート能力で得点を重ね、キャプテンを任せられるまでに至った。
柿谷は言う。「『サッカーやったらオレは負けへんで』っていうのもあったからこそ、徳島行っても『オレここでやったる』ってやれたし」
生活には「目覚まし時計」が欠かせないと言う柿谷。
「とりあえず目覚まし時計ね。オレの相棒。かわいいっしょ。徳島行ってから使ってるから、もう4年ぐらい。こいつが鳴ったら、もう終わりっす。オレの睡眠時間」
その音は、眠れる天才の眼をも覚ました。
■エース
去年(2012年)、柿谷曜一朗はセレッソ大阪に復帰を果たした(当時22歳)。
「今年はやりますよ、曜一郎は。天才。ほんとに」
そう言って柿谷の肩を叩くのは清武弘嗣(きよたけ・ひろし)。香川真司が海外に渡った後、「憧れの8番」はこの清武が継承していた。
徳島でプロの在り方を学んだという柿谷だったが、天才の回り道はもう少し続くことになる。
復帰はしたが、レギュラーとは認められずベンチ要員が続いた。開幕戦から数ヶ月、その出番はほとんどなかった。
それでももう、柿谷は腐らなかった。控え組の練習試合でも決して手を抜こうとはしなかった。
柿谷「昔やったらね、練習試合やしって思いやったんですけど、今はこういう試合から一個一個大事にしたいっていう思いがあるんで」
いよいよ時は満ちる。
シーズン途中でポジションを奪った柿谷は、2012年40試合に出場して17得点。トレードマークであった長髪は切り落とされていた。
そしてついに、憧れ続けた8番が柿谷のものとなる(2013年1月)。
「背番号8番、柿谷曜一朗!!」
ついに背負ったエースの証。
「カッコええやん」と言われて、まんざらでもない。
柿谷「そら、カッコええよ。もう、これは。カッコいいよ」
彼がチームの選手紹介に載せた一言はこうである。「背番号8番。誰もがこの時を待っていた。真のエースとして、セレッソに新しい歴史を刻むべく全力を尽くす覚悟でシーズンに臨む」
8番をつけた柿谷は今シーズン(2013)、その重みに恥じない活躍を続けている。
昨シーズンは14位と低迷したセレッソ大阪であったが、今季は優勝争いを続けている。その原動力となっているのは言わずもがな、柿谷曜一朗である。チームトップの15得点(9月22日現在)。

■天才弾
天才は2度輝く。
かつて「日本サッカーの将来を背負う」とまで期待された逸材は、いよいよ日本代表での活躍もはじまった。
2013年 東アジアカップ
「柿谷2発! 天才弾!」
宿命の対決、韓国戦はこの男の独壇場となった。
”シュート数は韓国の9に対して、日本はわずか5。終始、押し込まれる展開が続くなか、1トップに入った柿谷が2本のシュートをいずれもゴールに結びつけた(Number誌)”
圧巻だったのは、1 - 1の同点で迎えた後半ロスタイム。
「一回、踏ん張ったん分かりました?」と柿谷が言う通り、ゴール前、韓国のゴールキーパーが弾いたボールが柿谷の眼前に来た時、彼は一瞬、タメをつくっている。
柿谷「ここでボールに走って行く(前に行く)んじゃなくて、一回後ろに引いてるでしょ、左足」
”GKが弾いたこぼれ球を、柿谷曜一朗がニアのコースを消そうとする相手の逆をとってファーサイドに左足で蹴り込んだ(Number誌)”
コンマ数秒の間(ま)、その間によって敵の背後にシュートコースが生まれた。
柿谷「急いで前行って蹴ってたら、たぶん止められてたんすよ。で、ちょっと待ったんすよね。もうちょっとゆっくり打てたら、もっとカッコよく入ってたかな」
”ゴールの瞬間、ザッケローニ監督も興奮を抑えられないように、何度も小刻みにガッツポーズを続けた(Number誌)”
この逆転弾が、日本の優勝を文句なく確定した。
2試合連続ゴール、計3得点を決めた柿谷曜一朗は、この大会のMVP(最優秀選手賞)を獲得。
U-17(17歳以下)ワールドカップから6年、久しく途絶えていた柿谷曜一朗の名が、ふたたび世界に響くこととなった。
早く熟するかと思われた天才の、少々遅れはしたがしかし、華々しい代表デビューであった。

■プレッシャー
天才、天才と囃し立てられる柿谷曜一朗。
だがいつしか、彼はその呼び名を好まないようになっていた。
「もう僕は弱いですから。はっきし言って、めちゃくちゃ弱いですから。僕はもう、ほんまにプレッシャーとかにも弱いし。自分が一番よくわかってるから」と柿谷は言う。
あの韓国ゴールに叩き込んだ豪快な決勝弾も、その心境をこう語る。
「もうド緊張でしたよ、オレ。心臓バクバクでしたから。『ボール来てもうた』って感じで、ヤバイ、ヤバイって思って。こんなチャンス外したら、後で何言われるか分からないって思って」
そのくせ、冷静にタメまでつくって狭いシュートコースを見極めたその力量は、周囲が「天才、天才」と言葉を重ねる所以であろうか。
代表デビューを果たした後、柿谷は憧れの選手、セレッソかつての8番・森島寛晃と言葉を交えた。
森島「若い頃につけた日の丸と、今の日の丸の重みはやっぱ違う?」
柿谷「ぜんぜん違いますね。やっぱ、全員見てるし。まぁ、それがプレッシャーになって出来へんようになるのが一番ダメなんで。その経験はもう、僕はしたので(笑)」
そんな素直な柿谷の言葉に、森島も笑う。
■日本代表
”10代の頃、天才の呼び名をほしいままにした男は、今年に入って突如蘇ったのでも台頭したのでもない。傷つき、学び、気づき、獲得し、そして少しばかり爪を隠し、『2013年の自分』に至ったのである。変わったはむしろ周囲だった(Number誌)”
代表チームのステイタスが異常に肥大化した日本。
”代表チームに招集されない限り、国民的な注目を集めることはまずない。どれだけ美しいゴールを決めたところで、注目を集めるのは代表選手の平凡なゴールということになる(Number誌)”
今回、東アジアカップを戦った「東アジア組」は、”悪い言い方をすれば、国内からの寄せ集め(Number誌)”。
”ザック・ジャパン本来にメンバーに食い込めるかどうかの選抜テスト。ザッケローニもハッキリとそう語っている(同誌)”
このテストに文句なしでパスした柿谷曜一朗。以後、代表戦でのプレーが続き、「国民的な注目」を集めることになる。
8月14日 ウルグアイ戦
9月6日 グアテマラ戦
9月10日 ガーナ戦
「本田(圭佑)選手としゃべったことなかったんすか?」
その質問に柿谷は「ないです、ないです。みんなそうやって言いますけど、ほんま、しゃべったことない人ばっかりですよ」と手を振り、はじめての「海外組」との印象を語る。
「内田(篤人)選手、メッチャ男前ですね、あの人。初めて見ましたけど、女の子がそりゃキャーキャーなるのが分かりました。思ってた通りすぎた人は岡崎(慎司)選手です。ええ人なんやろなぁ、話しやすい人なんやろなぁって思ってたら。その通りでした。全員にいじられてました(笑)」
■今の曜一郎
柿谷は真面目に言う。「8番つけちゃいましたから。やっぱりこのクラブ(セレッソ大阪)でこの背番号をつける以上、自覚をもってやらないと」
かつて、柿谷曜一朗の魅力といえば、”もっと生意気で、相手をおちょくって、みたいなところがあった(Number誌)”。
それは捨ててしまったのか?
柿谷「忘れてないですよ。いまも持ってます。ただ昔の僕は、それをやっていい時といけない時の区別がつかなかった。そのあたりの区別はちゃんとつけなあかんと思えるぐらいにはオトナになりました(笑)」
かつての生意気な曜一郎は、時おり顔を出す。たとえば、初の海外組とのプレーとなったウルグアイ戦後、こう豪語している。
「初めてやったんですよ、ああいう名前のある人らとやるの。だから、どんなもんかなっていう感じもあったし。あれ(ウルグアイ代表)が世界いうんやったら、日本はワールドカップで優勝できると思うし」
ちなみにこの一戦、日本はウルグアイに「0 - 4」で完敗を喫しているのだが…(柿谷は先発、後半19分交代)。
柿谷を小学生の頃から見てきている小菊昭雄氏(セレッソ大阪コーチ)は、こう言う。
「雰囲気が変わってきました。一番印象的だったのは、まだ曜一郎が控えに回ることが多かった昨シーズン序盤、味方が点を取った時、一番喜んでいるのがアイツやったんです。昔の曜一郎は、勝っても負けても自分が満足ならええわっていうところのあった子やったんですが」
昔の曜一郎は、怖いもの知らずで無鉄砲で、良くも悪くもエゴイスト…。
小菊コーチは続ける。「曜一郎が確固たる自信と立場を手にした時、僕は16〜17歳の、もっと言えば12〜13歳の頃の『とてつもなかった曜一郎』が、今の曜一郎にプラスαされてくるんじゃないかと思ってるんです。正直、楽しみで仕方がありません」
「たぶん、真司(香川)も意識しているでしょうね。意識する対象は本田選手をはじめたくさんあるでしょうけど、間違いなくそこに曜一郎の名前は入っているはずです。で、彼らが共演したとき、『世界をしびれさせるサッカー』をやれる可能性はあると思います」
次の代表戦は10月12日。
ヨーロッパ遠征の幕開けだ。
”完成した天才よりも、可能性を秘めた未熟者でありたい”
柿谷曜一朗

(了)
関連記事:
若き香川を育てた名伯楽「クルピ」。その秘密とは?
マンU移籍1年目、香川真司は「赤い悪魔」になれたのか [サッカー]
ドイツの期待を背負った王様「清武弘嗣(サッカー)」
ソース:
情熱大陸「プロサッカー選手・柿谷曜一朗」
Number誌「日本代表はブラジルに勝てるはずなんです 柿谷曜一朗」